

芳香療法・アロマテラピー
芳香療法(アロマテラピー)は三千年以上も前からインド、中国で治療に使われていました。昔の人は香りの効用にひそかに気付き、上手に利用してきました。現代人はストレスがなにかとたまりがち。いい香りは疲れた体と心をいやす「リラックス空間」をつくつてくれます。自分に合った香りを選んで、体にいい香りのパワーを上手に取り入れましょう。アロマテラピーに使用されるエッセンシヤルオイルには色々な種類があり、一つひとつ異なる効用をもっています。
エッセンシヤルオイルの基本的な働きは、
① 体の機能を調整する② 細菌の成長を防ぐ
③ 体のリズムを調整する
④ 精神状態を改善させる
の4つの働きです。
空腹時に、食べ物のにおいを嗅ぐと、唾液が出てくるように、香りは、脳に情報を伝達します。様々な情報が脳に送られることで、眠くなつたり、落ち着いたりします。お腹が痛いときに、いい香りをかぐことで自律神経系に情報を伝達し、痛みが和らぎます。このように上手に香りを使うことで、体の不調をいやすことができるのです。そのほかに、香りを空気中に漂わせて、細菌の発育を阻止したり、また、海外旅行に出かけて時差ぼけになったときでも、香りをかぐことによって体内時計が正常に戻り、生活リズムを取り戻すことができます。
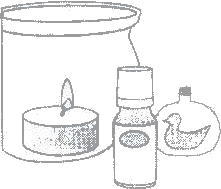
ただし、アロマテラピーの本の通りに試しても効かないことがあります。どんな人でも、過去にかいだことのある香りが脳に記憶されていて、同じ香りをかぐと、そのときの心理状態と同じ気持ちになります。ですから、同じ香りで誰もが同じ効果を得られるとは限りません。とってもリラックスしていた時にかいだ香りを使えば、心が安静になるでしょう。過去の記憶を上手に使うことで、自分だけの効用を見つけることができます。リラクゼーションを求めるなら、まず自分に合った香りを探すこと。いくら効用のある香りでも嫌いなにおいだったら、あまり心理的効果は望めません。
好きな香りを探して少しずつ試して慣れてきたら、オリジナルのブレンドを作っていけばアロマテラピーの楽しさがさらに増すでしょう。
芳香浴の楽しみ方
◎ ティッシュペーパーにたらす コットンやティッシュペーパーに1~2滴たらし、香りを鼻から吸入する。特に、花粉症にはユーカリがおすすめです。◎ カップやボウルで カップやボウルなどの容器に3~5滴たらし、熱湯を注ぎます。部屋に香りが広がります。
◎ 入浴
 お風呂に4~5滴たらして深呼吸すれば、たちまちリラックスできます。眠れない夜は、ラベンダー。朝はローズマリーがおすすめです。
お風呂に4~5滴たらして深呼吸すれば、たちまちリラックスできます。眠れない夜は、ラベンダー。朝はローズマリーがおすすめです。◎ 香炉、アロマライト
 香炉はポピュラーな楽しみ方で、部屋全体に香りが広まり、持続します。夜寝るときは、アロマライトが火の気の危険がないのでおすすめです。
香炉はポピュラーな楽しみ方で、部屋全体に香りが広まり、持続します。夜寝るときは、アロマライトが火の気の危険がないのでおすすめです。◎ 香り袋 好きな香りを袋に入れて枕元に置くとよく眠れます。タンスの中に忍ばせるのもいい方法です。
| 自然の力で悩みを解消してくれるエッセンシヤルオイルたちを紹介しましょう | ||
| ●不眠症● | ||
| ラベンダー | 作用 | 鎮静、消炎、細胞修復、抗菌、防虫、生体リズム調整 |
| 適応 | 心身の緊張、不眠、高血圧、筋肉痛、便秘、水虫、時差ぼけ | |
| ベルガモット | 作用 | 緩和、高揚、抗菌 |
| 適応 | 心身の疲労、不眠、食欲不振、精神疲労や不安による抑うつ症状、尿道炎、膀胱炎 | |
| ●生理痛● | ||
| ローマンカモマイル | 作用 | 鎮静、緩和 |
| 適応 | 神経過敏、不眠、神経性消化器障害、筋肉と消化器系のけいれん、月経前症候群、月経前緊張症 | |
| クラリセージ | 作用 | 鎮静、緩和、ホルモン分泌調整 |
| 適応 | 非嘆、孤独感、不安などの抑うつ症状、月経前症候群、更年期障害 | |
| ●ストレス● | ||
| イランイラン | 作用 | 緩和、高揚、ホルモン分泌調整 |
| 適応 | 過度の緊張に伴う頻拍、過呼吸、高血圧、自信喪失などの抑うつ症状、月経前症候群 | |
| サンダルウッド | 作用 | 鎮静、排尿、抗菌 |
| 適応 | めい想時、心身のクールダウン、尿道炎、膀胱炎 | |
| ●月経前症候群● | ||
| ゼラニウム | 作用 | 媛和、高揚、ホルモン分泌調整 |
| 適応 | 心身の緊張による情緒不安定、月経前症候群、更年期障害 | |
| ●イライラする● | ||
| ローズ | 作用 | 緩和、高揚、ホルモン分泌調整 |
| 適応 | 神経過敏、非嘆、情緒不安定、月経前症候群、更年期障害、女性生殖器系の不調、セクシャリティーの欠如 | |
| ネロリ | 作用 | 緩和、高揚、細胞修復 |
| 適応 | 心身の緊張、不安、不眠、月経前症候群、更年期障害 | |
| ●寝起きが悪い● | ||
| ローズマリー | 作用 | 消化器系機能調整、血液循環促進、老化防止 |
| 適応 | 心身の疲労、老化に伴う記憶力低下、集中力の低下、ぼけ症状、胃腸・肝臓・胆のうの機能低下、便秘、肩こり、腰痛、頭痛、リウマチ、通風、関節炎の予防効果 | |
アロマテラピー(芳香療法)
香りの効用と注意点アロマセラピーとは
アロマセラピーとは、植物より摘出された精油(エッセンシヤル・オイル)の香りや薬効成分を使って、心身の治療を行う植物療法の一つです。アロマはギリシャ語でスパイスや香りを、セラピーは治療法を意味します。欧米では、代替医療や補助療法の一つとして医療分野で行われていますが、日本ではエステなど医療機関以外で行われるケースが多く、事故が増えています。また、欧米では医薬品である精油が、日本では基準もないまま、町の雑貨屋などで乱売されています。粗悪な品質と知識不足によって接触性皮膚炎などのトラブルが起こつているものと思われます。
宣伝文句を鵜呑みにしてはいけない
「天然のものなので副作用の心配がない」とか、「天空からのパワーが詰まっている」など根拠のない宣伝文句が横行していますが、鎮痛剤を飲むと胃壁を荒らすように、どんな薬でも効果を期待するとある程度の副作用はあるものです。副作用がないと宣伝しているのは問題です。
精油購入上の注意
精油を購入する際は、
① 原料のハーブの植物学上の名前 (ラテン名)の記載があるか
② 原産国が明記されているか
③ 内容成分が提示されているか
などを確かめて、医療関係者など知識を持った人から十分なアドバイスを受けてください。
ローソクを使ったアロマキャンドルが使われるケースが多いのですが、精油を高温にさらすと内容成分は変性して効果がなくなります。ローソクによる火事も散見されるので、注意が必要です。
国民生活センター『くらしの豆知識99』より